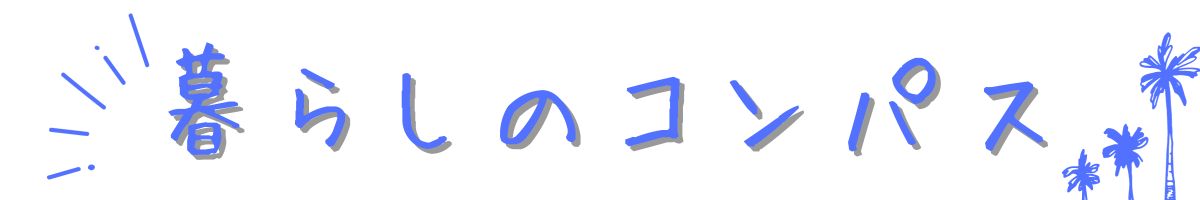「うちの子、ハサミやお箸が苦手で…」
「工作や絵を描くのがうまくできないみたい」
そんな“手先の不器用さ”に、不安を感じる保護者の方は少なくありません。
けれど、発達には個人差があり、手先の器用さも後からグンと伸びる子がたくさんいます。
この記事では、10年以上にわたり障害福祉に携わってきた社会福祉士の視点から、家庭でできる「遊びのトレーニング」を年齢や発達段階に合わせてご紹介します。
「遊びながら、自然にできるようになる」──そのためのヒントを、ぜひご家庭で活かしてみてください。
手先が不器用ってどういうこと?|よくある特徴
- ハサミや鉛筆を正しく持てない
- 穴に紐を通す作業が苦手
- 粘土遊びや折り紙を嫌がる
- 服のボタンやチャックができない
- お絵かきや文字が歪む・薄い
このような“困り感”がある場合、「微細運動(びさいうんどう)」の発達がゆっくりかもしれません。
ただし、不器用さ=発達障害ではありません。
発達のグラデーションの中で「あと少し育ててあげたい部分」と捉えると、前向きにサポートできます。
【年齢別】手先のトレーニング遊び5選
1. 2〜3歳|感覚と動きの基礎を育てる
① 洗濯バサミ遊び
紙コップや厚紙に洗濯バサミをつけたり外したりするだけ! 指の分離運動と握力を育てます。
② 指スタンプ遊び
絵の具やスタンプパッドを使って自由にポンポン。指先の動かし方を学びながら、色や形の感覚も育ちます。
2. 4〜5歳|細かい動きに挑戦
③ ビーズ通し
大きめビーズに毛糸や紐を通す遊び。集中力も必要なので、就学準備にもぴったりです。
④ おはしでつまむゲーム
スポンジや綿玉をお皿に移すだけでもOK。鉛筆やお箸の持ち方の基礎になります。
3. 6歳〜|遊びから日常生活へ
⑤ 自分だけの工作セット
ハサミ・のり・テープなどを用意して、自由に制作!
「作りたい→手を使う」プロセスで、楽しみながら実践力が伸びていきます。
テーマ別|不器用さをサポートする遊びアイデア
「握る力」が弱い子には…
- 粘土こね遊び
- 風船バレー(ラケットでたたく)
- 絞りタオルレース
「指先のコントロール」が苦手な子には…
- シール貼り台紙
- 穴あけパンチ遊び
- ピンセットで豆移動ゲーム
「力加減」が難しい子には…
- トングでゼリー運び
- 牛乳パックを握って潰す遊び
- ぬりえ&クレヨンで色の濃淡遊び
家庭で取り入れるコツ3つ
1. 「楽しい」が第一!
上手にできなくてもOK。「できた!」よりも「できるようになってきたね」と声をかけるのがコツです。
2. 苦手を“遊び”でカバーする
ハサミが苦手なら、紙ちぎり遊びから始めましょう。
「できないこと」ではなく「楽しくできる工夫」を。
3. 比較せず、少しずつの成長を見守る
周りの子と比べず、昨日のわが子と比べて「今日できた」を喜びましょう。
よくある質問(Q&A)
Q:お箸がどうしても上手に持てません。
→ 最初は“トレーニング箸”を使ってOK。慣れてきたら普通のお箸に切り替えていきましょう。焦らず、段階を大切に。
Q:道具を嫌がることがあります。
→ 無理に使わせず、手遊び歌やごっこ遊びなどから始めて、自然に興味が出てくるのを待ちましょう。
おわりに|「不器用さ」はゆっくり育つ力
手先の器用さは、日々の遊びや生活の中で少しずつ育まれるもの。
「この子はこの子のペースがある」と信じて、毎日を“遊びのチャンス”に変えていきましょう。
そして、もし気になることがあれば、地域の発達相談や療育施設、保健センターの社会福祉士などに気軽に相談してみてくださいね。