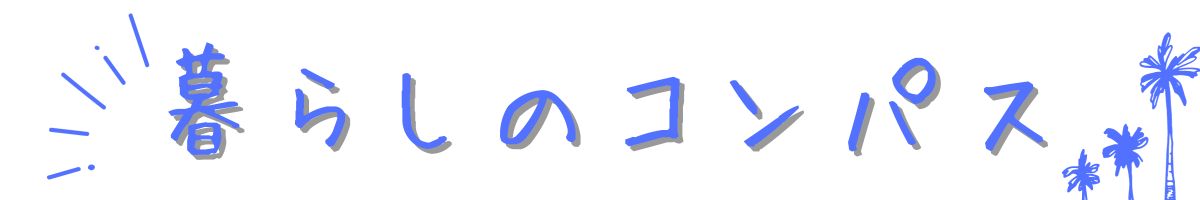「うちの子、話を聞いていない気がする…」「何度言っても伝わらない…」
そんな悩みを抱えるご家庭、多いですよね。実は“聞く力”は、もともと備わっているわけではなく、成長の中で少しずつ育てていく力なんです。
本記事では、社会福祉士・精神保健福祉士で障害福祉の現場10年の筆者が、「家庭で無理なくできる“聞く力”の育て方」をわかりやすく解説。
遊び・声かけ・環境の3つの視点から、今日から実践できるアイデアをお届けします!
「聞く力」とは?発達の基本を知ろう
- 聞く力=音をキャッチする力+意味を理解する力+集中して聞き続ける力
- 言葉の遅れや注意力の育ちにも影響
- 発達段階に応じて違いがある(例:2歳は“指差し+目線”の理解から)
こんな子におすすめ!「聞く力」が気になるサイン
- 名前を呼んでも振り向かない
- 指示が通らない、1つのことに集中できない
- よく聞き返す・すぐに動けない
※感覚過敏や発達グレーゾーンの可能性も含め、支援の第一歩に
家庭でできる!「聞く力」を育てる遊び 5選
- まねっこゲーム(模倣遊び)
→「〇〇してみて〜」の声かけからスタート! - 音あてクイズ
→鳴き声・生活音・楽器などの音源を使って「これはなに?」 - おつかいゲーム
→「赤いコップとスプーン持ってきて」など複数指示を練習 - お話づくりごっこ
→親が短い話をして「誰が?」「何してた?」と質問 - リズムあそび
→「ストップ!」や「ジャンプ!」など音と指示の一致を遊びで体験
声かけで意識したいポイント3つ
- 短く・はっきり・ゆっくり
→長文はNG!「おもちゃ、片付けようね」くらいが◎ - 視線を合わせる・名前を呼ぶ
→聴覚だけでなく視覚のサポートも使う - 成功したらすぐに褒める
→「できたね!」「聞けたね!」で自信を育てる
聞く力を伸ばす家庭環境づくり
- テレビや音の多い環境を見直す(雑音カットが集中に◎)
- 対話の時間を意識的に作る(ご飯中や寝る前の会話など)
- 保育園や療育機関と連携し、家庭でも実践
指示が通らない?具体例:朝の支度編
ママ:「ゆうくん、保育園行くからパジャマ脱いで、着替えてね〜」
ゆうくん:「うん!」(と言ってオモチャを手に遊びはじめる)
パパ:「また聞いてないのか…。ちゃんと“聞く”練習した方がいいよなあ」
ママ:「実はね、“聞いてない”んじゃなくて、“聞き取りきれてない”こともあるんだよ」
パパ:「え?どういうこと?」
ママ:「たとえば“着替える”って言っても、頭の中でイメージがまだ固まらないと、次の行動に移れないの。言葉の指示をイメージ化できる力がまだ未熟なんだよね」
【じゃあ、どうすればいいの?】
パパ:「じゃあさ、どうすれば“聞ける子”になるの?」
ママ:「ポイントは“具体的に、短く、視覚的に”伝えることかな」
方法①:1つずつ、区切って伝える
ママ:「たとえば『パジャマ脱いで、洋服着て、靴下はいて』って一気に言うと難しいんだよね」
パパ:「あー、確かに俺でも途中で忘れるかも(笑)」
ママ:「だからまずは『パジャマ脱ごうね』だけ。終わったら次に『Tシャツ着よう』って伝えるようにしてるよ」
方法②:視覚的に伝える(写真・イラスト・チェック表)
ママ:「最近は“やることリスト”作って、冷蔵庫に貼ってるんだ。絵カード風にしてね」
ゆうくん(チェック表を見て):「つぎは、ズボン!」
パパ:「すごいな、それ。視覚的なサポートって本当に効果あるんだな」
よくあるQ&A
Q. 何歳くらいから「聞く力」を育てられますか?
A. 1歳後半~2歳ごろから少しずつスタートできます!
Q. 発達に凸凹がある場合はどうする?
A. 無理なく「その子の今」に合わせた声かけ・遊びがベースです。
まとめ
「聞く力」は一朝一夕では育ちません。でも、毎日のちょっとした遊びや声かけの中で、少しずつ変化が見えてきます。
「できない」より「できた!」の瞬間を一緒に喜ぶことが、子どもの聞く力を伸ばす最大のコツです。