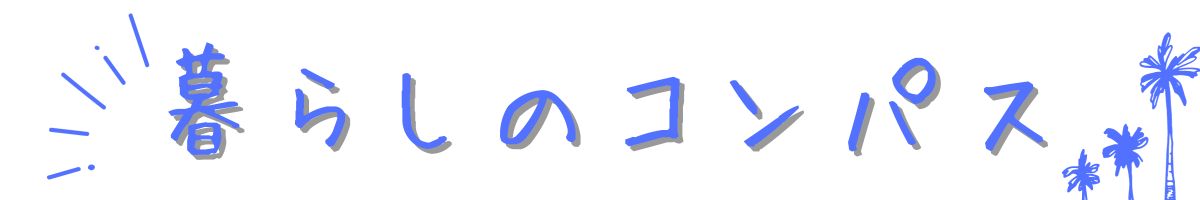「我慢ばかりさせていないかな…」
「上の子の心が心配…」
障害のある子どもを育てているご家庭で、兄弟児の心のケアに悩む方は少なくありません。
兄弟児は、親が気づかないうちに“感情を押し殺す”経験をしていたり、“自分の気持ちを後回しにする”ことに慣れてしまっている場合があります。
そんなとき、家庭でできる小さな支援として「絵本」はとても有効です。
本記事では、社会福祉士の視点から、兄弟児の“気持ちに寄り添う”絵本10選をご紹介します。
年齢別に分類しながら、絵本を使った声かけのコツや活用法もあわせてお届けします。
兄弟児とは?なぜ絵本が支援になるの?
兄弟児とは、障害や疾患をもつきょうだいがいる子どものことを指します。
兄弟児は小さなころから「我慢」「遠慮」「気遣い」を覚え、周囲に“いい子”として振る舞う傾向があります。
それは強さでもありますが、本音を伝える難しさや自己肯定感の低下につながることもあります。
そんな子どもたちにとって、「絵本」は気持ちを理解するツールであり、心の代弁者にもなってくれます。
【3〜5歳向け】兄弟児へのおすすめ絵本 3選
① 『わたしのワンピース』(こぐま社)
- おすすめポイント:空想の世界が広がる一冊。自由な発想と“自分らしさ”を楽しむ内容が、自己肯定感を育みます。
- こんなときに:弟や妹が注目されているときに。
🗣 声かけ例:「あなたの好きな模様のワンピースはどれだろうね?」
② 『ちょっとだけ』(福音館書店)
- おすすめポイント:妹が生まれたお姉ちゃんが「ちょっとだけ」我慢する姿と、それをちゃんと見ているママの姿に共感が集まる感動作。
- こんなときに:「お兄ちゃんだから」「お姉ちゃんだから」と言ってしまった後に。
🗣 声かけ例:「あなたも“ちょっとだけ”頑張ってるよね、ママわかってるよ。」
③ 『にじいろのさかな』(講談社)
- おすすめポイント:与えることの喜び・寂しさを描いた名作。兄弟との関係に悩むときのヒントに。
- こんなときに:弟や妹とのトラブル後に。
🗣 声かけ例:「あなたのキラキラ、誰かにあげたことあるかな?」
👧 【6〜8歳向け】兄弟児へのおすすめ絵本 4選
④ 『ぼくのニセモノをつくるには』(偕成社)
- おすすめポイント:完璧でいようとする子どもに、「自分らしくていい」と伝える一冊。兄弟児の“いい子願望”をほぐす内容。
- 感情ポイント:頑張りすぎる子へのメッセージとして。
🗣 声かけ例:「“あなたにしかできないこと”ってあるね。」
⑤ 『わたしがいどんだ戦い 1939年』(評論社)
- おすすめポイント:足の不自由な妹と暮らす少女の葛藤と成長を描く感動の長編絵本。共感性・深い理解を促す。
- 中学年向け:読んで感じたことを話し合う読後体験が◎。
⑥ 『ふたりはともだち』(文化出版局)
- おすすめポイント:兄弟ゲンカや仲直りのリアルを描いた一冊。兄弟の存在を“あたたかく”見直せるきっかけに。
⑦ 『おこだでませんように』(小学館)
- おすすめポイント:怒られがちな男の子の本音に、大人も胸が締めつけられる絵本。家庭の“安心感”を考えるきっかけに。
🧒 【9歳以上・思春期向け】兄弟児に響く絵本 3選
⑧ 『いつでも会える』(学研)
- おすすめポイント:別れと再会、心のつながりを描いた絵本。死や障害への“不安”を優しく包み込む。
⑨ 『あなたのことがだいすき』(角川書店)
- おすすめポイント:そのままのあなたが大好きというメッセージを伝える、シンプルながら深い愛情が詰まった一冊。
⑩ 『こどもたちはまっている』(亜紀書房)
- おすすめポイント:「ちゃんと見ていてほしい」子どもの本音に、大人が気づかされる一冊。自己肯定感を高めたいときに◎。
まとめ:絵本の活用で“心の居場所”を家庭に
兄弟児の心はとても繊細です。
日常の会話では言いにくい感情も、絵本を通せば伝え合えることがあります。
ポイントは、「読み聞かせの時間を“特別なひととき”にすること」。
毎日でなくても構いません。一緒に絵本を読むことで、“あなたのことを大切に思っている”というメッセージが、しっかりと伝わります。