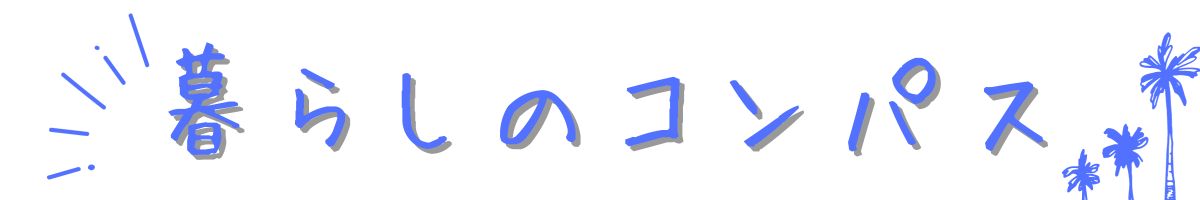「おうちでできる療育、何から始めたらいいの?」
「子どもの発達をサポートしたいけど、どんなグッズがいいのか分からない…」
そんな悩みを持つご家庭は少なくありません。療育とは、子どもの発達を支援するための専門的なかかわりですが、実は家庭でも気軽に取り入れられるグッズや知育アイテムが数多く存在します。
本記事では、障害福祉の現場で10年以上働き、社会福祉士・精神保健福祉士の資格をもつ筆者が、実際におすすめできる「家庭療育グッズ」を年齢別に10選ピックアップ。
発語・手先の動き・感覚統合・コミュニケーションなど、発達のさまざまな側面をサポートする知育アイテムを、目的別にわかりやすくご紹介します。
療育グッズって何?家庭で使う意味とメリット
◆ 療育グッズとは?
療育グッズとは、子どもの発達を支援するために作られたおもちゃや道具のことです。
遊びの中で楽しみながら、発語、手先の器用さ、バランス感覚などを育てることができます。
◆ 家庭で療育グッズを使うメリット
- 発達のサポートが日常の中でできる
- 子どもの得意・苦手を理解しやすくなる
- 親子のコミュニケーションが増える
- 子どもの自己肯定感を育てられる
【年齢別】家庭で使える療育グッズおすすめ10選
【1歳〜2歳向け】①フィッシャープライス バイリンガル・ラーニングボックス
- 【目的】音声刺激・因果関係の理解
- 【特徴】ボタンを押すと英語と日本語で話しかけてくれる知育おもちゃ。感覚遊びにも最適。
👨👩👧👦 親子で一緒にボタンを押して、「ワンワンだね!」「今、リンゴって言ったね」と言葉を増やせるきっかけに。
【1歳〜3歳向け】②くもん出版 くるくるチャイム
- 【目的】手の操作・因果関係の理解
- 【特徴】玉を入れるとカラカラと落ちてチャイムが鳴る仕組み。何度も繰り返し遊びたくなる仕掛けが満載。
👋 手を使う動作は「手先のトレーニング」にピッタリ。指先の動きは言葉の発達にもつながります。
【1歳~4歳向け】③ルーピング玩具(ワイヤービーズ)
- 【目的】手の操作・視覚追従・集中力
- 【特徴】カラフルなビーズをワイヤーに沿って移動させるおもちゃ。目と手の協応が育ちます。
✋ 集中して遊ぶことで、落ち着いて作業する力も育ちます。
【2歳〜4歳向け】④アンパンマン おしゃべりいっぱいことばずかん
- 【目的】語彙の習得・発語支援
- 【特徴】ペンでタッチすると音声が出る絵本。日常会話・単語・効果音が豊富で言葉の刺激にぴったり。
📚 発語に不安のあるお子さんにも大人気。繰り返し遊ぶうちに自然と語彙が増えます。
【2歳〜5歳向け】⑤感覚あそびカード144
- 【目的】バランス感覚・身体の使い方
- 【特徴】体を動かしながら遊ぶカード式の療育教材。室内でも運動遊びができ、感覚統合に効果的。
🚶♂️ 「ぐるぐる回る」「くぐる」など、遊びながら感覚の刺激が得られます。
【3歳〜6歳向け】⑥ピタゴラス(知育ブロック)
- 【目的】構成力・集中力・手先の巧緻性
- 【特徴】磁石入りのブロックで簡単に立体を作れる。空間認知や手の操作に最適。
🧱 作る→壊す→また作る、の繰り返しで創造性と指先が鍛えられます。
【4歳〜6歳向け】⑦図形モザイクパズル(くもん出版)
- 【目的】図形の合成・分解・回転の感覚を養う
- 【特徴】イラスト同士を合わせる簡単なパズル。難易度が調整できるため達成感を得やすい。
🧩 「できた!」という経験が子どもの自信につながります。
【4歳〜小学生向け】⑧タイムタイマー
- 【目的】時間感覚・見通しの力
- 【特徴】視覚的に時間が減っていくのがわかるタイマー。発達障害のお子さんにも人気。
⏰ 支援級や療育施設でも使われている定番ツール。「あと5分だよ」が視覚で伝わります。
【全年齢向け】⑨スライム・粘土遊びセット
- 【目的】感覚遊び・手指の感覚刺激
- 【特徴】柔らかい素材に触れることで、触覚を育てたりリラックス効果も期待できます。
👐 感覚過敏・鈍麻があるお子さんの感覚統合遊びにもおすすめです。
【全年齢向け】⑩くもんのはじめてのおけいこ
- 【目的】手先のトレーニング・準備学習
- 【特徴】太い線やシンプルな絵柄で、はじめてでも安心して取り組める教材。
✏️ なぞり書きは就学前の「書く準備」としても◎
療育グッズを選ぶときのポイント
- 子どもの発達段階に合っているか?
- 「できた!」という達成感を得られるか?
- 安全性が高く、誤飲の心配がないか?
- 親子で一緒に楽しめるか?
購入前には、レビューや対象年齢をしっかり確認しましょう。必要であれば、専門職(作業療法士や言語聴覚士)に相談するのもおすすめです。
まとめ|家庭でも楽しく、できる療育を
子どもの発達をサポートするために、特別な訓練や教材ばかりが必要なわけではありません。
今回紹介したようなグッズは、日常の遊びの中で「ことば」「動き」「感覚」「社会性」など、さまざまな力を育てることができます。
無理なく、親子で楽しみながら、毎日の中に少しずつ「療育のエッセンス」を取り入れていきましょう。